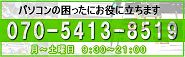2012年09月11日
事務用PCをwindows7に(後編)
前編では、パーツを机にならべた状態でwindows7のセットアップをしました。
後編では、実際に使用できるようにパソコンケースに取り付ける作業をします。
事務用PCは、古いFMVのケースを利用して組み立てていました→
マザーボード:GA-6VTXD
CPU:Pentium III-S 1.26GHz*2
メモリ:レジスタードSDRAM 256KB*4
windows2000で使用。
まず、ケーブル類を取り外して、古いマザーボードを取り出します。
←取り外し後。
ATX規格のケースは、マザーボード取り付けようネジの位置も決まっているので、同じATX規格のマザーボードでしたら、どのメーカーのものでも取り付けることができます。
但し、省スペースケースのような小さめのケースの場合は、大きめのマザーボードを取り付けできない場合もあります。
また、不要なネジ受けがある場合は、あらかじめ取り外すなど対応します。
今回使用するGA-P35-SD4を取り付け→
ATX規格のマザーボードなので、ピッタリ。
もちろん、最新のCore i 用も取り付けできます。
DVDドライブとハードディスクは、そのまま利用します。
←配線、各ケーブルを接続。
さらに、セットアップ済みのSSDも取り付け接続。
赤いSATAケーブルです(矢印)。
このマザーはCore2も載せることができますが、事務用なので、シングルコア最終型のP4 630を使用しています。
しかし、630はネットバーストアーキテクチャのCPUなので消費電力が大きい。
最大消費電力84W
これまで使用していたPentium3-Sの最大消費電力は30.4W
2つで60.8W
350Wの電源の交換はしないことと、PCIeのグラフィックカードの消費電力も考慮すると、P3sと同じ程度の消費電力に抑えたい。
そこで、CPUの電圧(Vcore)を標準より下げてみることに。
標準1.275V→1.14V(ソフト表示値)→
標準電圧より約10%の電圧ダウン。
消費電力は、電圧の二乗に比例するので、約20%のダウンに。
計算上は、
84W*0.81=68W
となりました。
60Wには及びませんでしたが、これで大丈夫でしょう。
発熱も減るので、純正ファンでも静かになるオマケつき。
3GHz動作で安定する電圧に調整しているので、オーバークロックは無理。
今回は、省電力に振りました。
ケースに全て組み込んだら、早速電源ON.
←無事windowsが起動しました。
BIOS設定で、SSDを優先ハードディスクに設定しています。
SATAはAHCIモード。
これで作業完了のはずでしたが、調べてみるとグラフィックカードがPCIe1xモードでの動作になている。
時々、一瞬、画面にモザイクのようなノイズがでることも。。。
どうも、カードの不具合らしいので、変更することに。
PV-T73G-UGF3(XFX製)→
ばっちり、16xモードで動作しました。
SSD対策として、ページファイル、マイドキュメント、インターネット一時ファイル、をSSD以外のDドライブへ移動。
これで、windows7化完了。
しかし、断念したことも。
SCSIカード
Logitec LHA-521U
のwindows7ドライバの提供なし。
vistaの時点から、SCSIはだいぶ切り捨てられたようです。
動作を軽めの設定にして、事務PCとして2週間ほど使用していますが、シングルコアでも十分使えますね。
SSDの効果もあるのでしょう。
遅ければ、CPUをCore2に変更する予定でしたが、その必要はなさそうです。
宛名印刷で、ワード2000の差込機能を使用するとエラーになりましたが、、データファイルを移動させ、ファイルの場所を指定しなおすことにより、エラーを解消することができています。
パソコン診療所
うえはら
Posted by パソコン診療所 at 19:37│Comments(1)
│Pentium4 630
この記事へのコメント
すごいですね
Posted by 保険見直しアドバイザー at 2012年09月11日 21:07